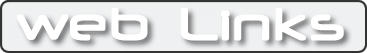リンク
RSS/ATOM 記事 (63336)
ここに表示されている RSS/ATOM 記事を RSS と ATOM で配信しています。


|
キーワード、腫瘍内マイクロドージング
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:43)
|
マイクロドージングとは、臨床試験(フェーズI)の開始前にヒトを対象に、臨床試験の投与量の100分の1程度の超微量(マイクロドーズ)の薬剤を投与し、高感度微量分析などによりその体内動態などを解析することで、安全性や有効性が期待できる薬剤を選別し、開発の成功確率を高める手法。
|
|
キーワード、架橋ナノゲル
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:42)
|
部分的に架橋され、網目構造を持つ高分子でできた粒子のこと。ナノゲルとは、粒径が100ナノメートル以下で、ゲル構造を持つナノ粒子を指す。
|
|
In The Market、時価総額100億円に満たない企業が3カ月間で急増
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:41)
|
日経BP・バイオINDEXは7月13日から30日にかけて、420から450の間で推移した。
|
|
業界こぼれ話、研究者にとって海外出張は無益なのか
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:40)
|
先日、あるメーカーのベテラン研究者が、「最近、中堅や若手研究者が海外出張に行きたがらない」とぼやいているのを聞いた。その企業では、研究活動の刺激になればと、希望する中堅や若手の研究者に海外での学会や展示会に出張する機会を与えている。しかし最近は、自ら「行きたい」と手を挙げる積極的な研究者がほとんどいなくなってしまったというのだ。
|
|
業界こぼれ話、取り扱い要注意のあの元経営者
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:39)
|
今から10年以上前、華々しく上場したバイオベンチャーがあった。仮にA社としておこう。A社は、遺伝子発現ネットワークの独自解析技術をベースに設立されたベンチャーで、複数の製薬企業と共同研究を行っていた。その後、海外の創薬ベンチャーと経営統合し、臨床段階の開発品の入手に成功。スーパーコンピューターを備えた大規模な解析センターを自前で開設するなど、上場までは順風満帆に見えた。
|
|
World Trendアジア、インドの薬剤政策案とOff-Patent HTA
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:38)
|
インドは世界最大のジェネリック医薬品の供給元だ。米国におけるジェネリックの需要の40%、英国の全医薬品の需要の25%がインド製のジェネリックによって満たされている。また、世界で使用されている抗HIV薬の80%がインドから供給されている。インドで製造されたジェネリックは、日本を含めて世界中に輸出されているのだ。
|
|
検証 企業価値、眼科にイノベーションは不要か(参天)
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:37)
|
眼科領域にフォーカスした参天製薬のビジネスモデルは、様々な提携を通じて得た全身薬を点眼薬へ展開する「ネットワーク創薬」であり、革新的な医薬品を自社から創出できているわけではない。ただしその企業価値は、他の製薬企業とは異なる観点で評価すべきだろう。革新的な医薬品により利益が大きく成長する可能性は低いものの、他方で特許満了の影響を大きくは受けにくく、着実に利益が成長する傾向を有する。
|
|
機能性食材研究(第56回)、アナゴ(穴子)
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:36)
|
機能性食材研究の第56回では、夏が旬のアナゴ(穴子)を取り上げる。7月5日は「穴子の日」と日本記念日協会に登録されている。ビタミンAなどのビタミン類やカルシウムなどが豊富で夏バテに効果的といえる。江戸前の天ぷらや、寿司の代表的な食材だ。関東では煮アナゴ、関西では焼きアナゴが好まれる。焼きアナゴをご飯にのせた穴子飯は瀬戸内海の名物だ。北日本の一部ではアナゴはハモと呼ばれる。
|
|
パイプライン研究、関節リウマチ治療薬(低分子化合物)
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:35)
|
自己免疫疾患のうち、関節リウマチの患者数が最も多い。世界保健機関(WHO)は、その有病率は0.3%から1%、女性に多い疾患と報告している。欧米では人口の約1%。国内の有病率は欧米よりも低く0.4%から0.5%とされ、全国では60万人から70万人の患者がおり、年間1万5000人が新たに発病するとの報告がある。
|
|
リポート、プロバイオティクス菌株の力自慢比較
from 日経バイオテクONLINE
(2018-8-6 0:34)
|
年始の人気スポーツ「箱根駅伝」で2018年1月、若手主体ながら往路優勝した東洋大学(総合は2位)。現在の猛暑とは逆の真冬のレースコンディショニングに、乳酸菌を配合したゼリー食品が選手に使用された。大塚製薬が2017年に発売した「ボディメンテ ゼリー」だ。
|