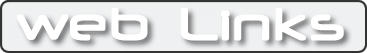リンク
RSS/ATOM 記事 (63329)
ここに表示されている RSS/ATOM 記事を RSS と ATOM で配信しています。


|
2018年度予算の健康・医療関連予算、AMED関連予算は2017年度から増額
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-25 8:00)
|
政府は2017年12月22日の閣議で、2018年度予算案と2017年度補正予算案を閣議決定した。健康・医療関連は、日本医療研究開発機構(AMED)予算が1266億円(文部科学省603億円、厚生労働省475億円、経済産業省183億円)と2017年度と比べて1億円の増額となる一方、各省庁の独法などが行うインハウス研究機関経費は759億円(文部科学省260億円、厚生労働省414億円、経済産業省85億円)と17億9000万円の減額となった。また、補正予算でAMEDへの出資金300億円が内閣府から計上された。医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE:Cyclic Innovation for Clinical Empowerment)の原資(2016年度第2次補正予算で出資された550億円)に追加される。
|
|
【機能性食品 Vol.316】、12月22日にミラクリントマトや「代謝改変(栄養改善)」評価合理化の審議始まる
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-22 12:00)
|
まずは、さきほど閣議決定された予算です。2017年度補正予算と2018年度当初予算を一体的に執行するのが、農林水産省の予算の特徴です。補正予算では、欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)の交渉妥結を踏まえ、国産発酵微生物を活用したチーズに取り組むようです。
次は、「機能性表示食品制度届出データベース 届出情報の更新」です。この1週間で更新があったのは12月18日(月)と12月20日(水)の2回でした。届出受理が公表された最終の届出番号は「C287」。この1週間で12件増えました。撤回が増えていなければ、有効な届け出件数の総数は、1167件になったと計算できます。
|
|
農水省、2017年度補正予算で国産発酵微生物活用チーズ
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-22 12:00)
|
農林水産省の2017年度補正予算と2018年度当初予算の政府案が、2017年12月22日に閣議決定された。バイオテクノロジーとの関係性が一番多い農林水産技術会議の予算について紹介する。
|
|
【日経バイオテクONLINE Vol.2830】、年の瀬にまとまった化血研の事業譲渡
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-22 10:30)
|
先日公開した本誌最新号のリポートで、韓国のゲノム医療について取り上げました。詳しくはぜひお読みいただければと思いますが、2017年3月から韓国政府が始めたのは、自家調整検査(LDT)と同様の枠組みを作り、多くの患者に安くパネル検査を提供しようという取り組みです。日本にとって、参考になるところもあるので、ぜひお読みください。
|
|
メディネット、Histogenics社から自家培養軟骨を導入
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-22 8:00)
|
メディネットは、2017年12月21日、米Histogenics Corporation社から、自家培養軟骨「NeoCart」の国内での開発と販売を独占的に行うライセンス契約を締結したと発表した。2018年後半にも膝関節軟骨損傷を対象とするフェーズIIIを開始し、2021年に再生医療等製品として本承認の取得を目指す。
|
|
結核ワクチンの開発を手掛けるクリエイトワクチンが解散へ
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-22 8:00)
|
大日本住友製薬および産業革新機構は2017年12月21日、日本ビーシージー(東京・文京、林一信社長)と共同で設立したクリエイトワクチン(大阪市、土田敦之社長)の解散を決定したと発表した。
|
|
英国でのCVCによるバイオテク投資は5年前の6倍に
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-22 8:00)
|
英国におけるコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)によるバイオテク企業への投資は、2015年には2010年の約6倍に成長したことが、英国製薬工業協会(ABPI)がまとめた報告書で明らかになった。ABPIが2017年12月14日発表した。
|
|
Merck社、ペムブロリズマブを胃癌患者らに第2選択薬として用いたPIIIでエンドポイント達成できず
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-22 8:00)
|
米Merck社は、2017年12月14日、ペムブロリズマブのフェーズIIIピボタル試験KEYNOTE-061で、主要エンドポイントを達成できなかったと発表した。061試験は、オープンラベルの無作為化フェーズIIIで、パクリタキセルおよびフッ化ピリミジンが第一選択として併用されたが、その後に進行を見た、胃または食道胃接合部の進行した腺癌の患者592人を登録し、1対1で、ペンブロリズマブ(200mgを3週間隔で静注)、または、パクリタキセル(80mg/平方メートルを28日サイクルの1日目、8日目、15日目に静注)に割り付けて、単剤投与したもの。
|
|
理研田中ユニットリーダーら、1細胞解析用アガロース微細構造体を開発
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-22 8:00)
|
理化学研究所生命システム研究センターの一細胞遺伝子発現動態研究ユニットの谷口雄一ユニットリーダー、集積バイオデバイス研究ユニットの田中陽ユニットリーダーらの共同研究チームは、遺伝子発現や細胞分裂速度などの細胞個性を1細胞ごとにハイスループット解析する微細構造体を作製し、大腸菌の増殖を細胞個別に測定することに成功した。本研究成果は、2017年12月21日のScientific Reportsオンライン版に掲載された。
|
|
JSR、PDXマウス構築に強みを持つ海外ベンチャー企業を買収
from 日経バイオテクONLINE
(2017-12-21 8:00)
|
JSRは、2017年12月20日、非臨床の医薬品開発受託機関(CRO)である英Crown Bioscience International社を買収して完全子会社にすると発表し、同日、都内で記者会見を開催。Crown社は、免疫不全マウスに、患者の癌組織を移植したPatient derived tumor xenograft(PDX)マウスの構築に強みを持つ。買収額は約440億円だ。
|