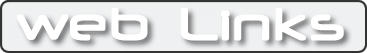リンク
| メイン | 登録する | 人気サイト (top10) | 高評価サイト (top10) | おすすめサイト (8) | 相互リンクサイト (3) |
| カテゴリ一覧 | RSS/ATOM 対応サイト (19) | RSS/ATOM 記事 (63257) | ランダムジャンプ |
RSS/ATOM 記事 (63257)
ここに表示されている RSS/ATOM 記事を RSS と ATOM で配信しています。


| OriginOil社、Idaho国立研究所の藻類バイオ燃料プロジェクトに参加 from 日経バイオテクONLINE (2015-2-2 0:00) |
|
米OriginOil社は2015年1月27日、米エネルギー省(DOE)傘下のIdaho National Laboratory(INL)が主導する藻類由来のバイオ燃料プロジェクトに参加すると発表した。DOEに提案したこのプロジェクトは、藻類バイオ燃料の生産効率を高めるため、斬新なアプローチの開発とその実現に焦点を当てている。
|
| 創薬ベンチャーのソレイジア・ファーマ、中国で営業拠点を整備へ from 日経バイオテクONLINE (2015-2-1 20:44) |
|
ソレイジア・ファーマ(東京・港、荒井好裕社長)は、2015年中に3番目の開発品目を導入する。本誌の取材に対して、同社の篠崎康二・経営企画室長が明らかにした。
|
| 米Naurex社、フェーズIIでNRX-1074が大鬱病性障害の症状を軽減 from 日経バイオテクONLINE (2015-2-1 0:00) |
|
米Naurex社は、2015年1月27日、大鬱病性障害患者に、経口投与も可能なN-methyl-D-aspartate(NMDA)型グルタミン酸受容体修飾薬であるNRX-1074を単回静脈内投与したフェーズIIで、患者の生活に大きな影響を及ぼすレベルの鬱症状の軽減が見られたと発表した。
|
| 米Goodwin社、Transporin社からトランスポーターペプチドMBDをライセンス from 日経バイオテクONLINE (2015-2-1 0:00) |
|
米Goodwin Biotechnology社は、2015年1月28日、米Transporin社と協力契約を結び、Transporin社が保有するヒトインスリン様成長因子結合蛋白質-3(IGFBP-3)の金属結合ドメイン(MBD)をカバーする知的財産権の世界での独占的なライセンスを得ることになったと発表した。
|
| 安価な筋電義手「Handiii」実用化を目指す Exiiiのプロモ動画 from 森山和道 (2015-1-31 13:09) |
|
Tweet
最近はすっかり有名な、3Dプリンター等を用いて安価な筋電義手「 Handiii 」の実用化を目指している exiii のプロモ動画。
|
| Algenol社、インドで藻類由来燃料を生産するデモンストレーション・プロジェクトがスタート from 日経バイオテクONLINE (2015-1-31 7:40) |
|
米Algenol社は2015年1月21日、インド最大手の天然資源開発企業であるReliance Industries社と協力して、インドで最初となるAlgenol社の藻類生産プラットフォームを展開するプロジェクトがスタートしたと発表した。デモンストレーション・モジュールは、インドJamnagarにある世界最大規模を誇るReliance社のリファイナリーに近接して設置された。
|
| Today on New Scientist from New Scientist - Online news (2015-1-31 2:30) |
|
All the latest on newscientist.com: pioneers of the bitcoin rush, big bang leak, how metadata reveals your secrets, Möbius strips of light and more
|
| 動画をGIFに変換する「Video to GIF」 from 森山和道 (2015-1-31 1:59) |
|
Tweet
「 Video to GIF 」を試しに使ってみました。
元の 動画はこちら 。
|
| Sync your sport to your body clock for a personal best from New Scientist - Online news (2015-1-31 0:21) |
|
Larks and night owls perform drastically better if a sporting event is timed to suit their circadian rhythm
|
| Cancer-warped skeletons imagined for building design from New Scientist - Online news (2015-1-31 0:00) |
|
The extreme deformities caused by bone cancer push the human body to its limits. Our amazing ability to adapt could inspire future architecture
|