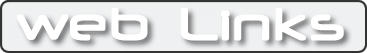|
Doudna氏ら設立の米Scribe社、Sanofi社との契約を拡大しin vivo遺伝子治療を開発
from 日経バイオテクONLINE
(2023-7-28 7:00)
|
ノーベル化学賞受賞者のJennifer Doudna氏らが設立した米Scribe Therapeutics社は2023年7月17日、フランスSanofi社との提携を拡大し、in vivo遺伝子治療の開発を進めると発表した。契約一時金は4000万ドル(約56億円)。両社は2022年秋にがんに対するex vivoナチュラルキラー(NK)療法の開発を目的とする協力契約を結んでいた。
|
|
小崎J太郎のカジュアルバイオ、森永乳業、ビフィズス菌の新生児への投与でビフィズス菌優勢菌叢が形成
from 日経バイオテクONLINE
(2023-7-28 7:00)
|
森永乳業が、健康な正期産児にビフィズス菌を早期投与することで、ビフィズス菌優勢の菌叢形成が促進されることを確認した。さらに排便回数が減少し、腸内の酢酸や分泌型免疫グロブリンA(sIgA)の分泌を高めることなど、有益な生理機能も見られた。同社はこの成果を、2023年6月27〜28日に開催された第27回腸内細菌学会学術集会と、Nutrients誌で論文発表した。
|
|
Novo社、心代謝性疾患の核酸医薬に米Eleven社のRNA送達技術を導入
from 日経バイオテクONLINE
(2023-7-28 7:00)
|
デンマークNovo Nordisk社と米Eleven Therapeutics社は2023年7月17日、核酸医薬を標的に正確に送達する技術を導入する契約を締結したと発表した。核酸に結合するコンジュゲートを同定するEleven社の「DELiveri」プラットフォームを活用し、糖尿病や心血管疾患など心代謝性疾患を適応とした、臓器特異的に送達する核酸医薬の研究を共同で実施する。
|
|
Eli Lilly社、体脂肪を減らす抗体医薬を開発する米Versanis社を買収
from 日経バイオテクONLINE
(2023-7-27 7:00)
|
米Eli Lilly社は2023年7月14日、心血管代謝疾患に対する治療薬の開発に取り込む米Versanis Bio社の買収に関する正式な契約を結んだと発表した。Versanis社はアクチビンとミオスタチンに作用する肥満症向けの抗体医薬を開発している。契約一時金と、開発と販売の段階で支払われる予定のマイルストーンなどを含めた総額は、最大19億2500万ドル(約2720億円)となる見込み。
|
|
厚労省第一部会、ノバルティスファーマのチロシンキナーゼ阻害薬などの一部変更など了承
from 日経バイオテクONLINE
(2023-7-27 7:00)
|
厚生労働省は2023年7月24日、薬事・食品衛生審議会第一部会を開催した。ノバルティスファーマの「ジャカビ錠」(ルキソリチニブリン酸塩)について、造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(GVHD)の適応を追加する一部変更が了承された。さらに、アレクシオンファーマの「ソリリス点滴静注」(エクリズマブ[遺伝子組換え])について、全身型重症筋無力症の適応を追加する一部変更が了承された。また、全薬工業の「リツキサン点滴静注」(リツキシマブ[遺伝子組換え])について、既存治療で効果不十分なループス腎炎の適応を追加する一部変更が了承された。
|
|
体温上昇で腸内細菌が作る胆汁酸がウイルス性肺炎の重症化を防ぐ研究成果を発表
from 日経バイオテクONLINE
(2023-7-27 7:00)
|
東京大学、慶應義塾大学、順天堂大学などの研究グループが、体温が上昇することでウイルス性肺炎の重症化が抑えられる現象に、腸内細菌が関わっていることを突き止めたと発表した。体温の上昇に伴い、腸内細菌叢から胆汁酸が産生され、それが好中球による局所的な炎症反応を抑えているとみられる。論文は2023年6月30日、Nature Communications誌に掲載された。
|
|
京大など、乳がんの起源となる遺伝子変異が思春期前後で生じていたと解明
from 日経バイオテクONLINE
(2023-7-27 7:00)
|
京都大学大学院医学研究科腫瘍生物学講座の小川誠司教授らの研究グループは、乳がんの起源となる遺伝子変異が、乳がんを発症する数十年前の思春期前後で生じていることを見いだした。同研究チームは、乳がん患者の組織を集め、全ゲノム解析を実施し、それぞれの遺伝子発現の類似点や相違点を基に系統樹を作成した。その上で、がんの原因となる遺伝子変異が生じた時期を推定したところ、思春期前後にはがんの原因となる遺伝子変異が起こっていると推察された。論文は、2023年7月26日、Nature誌にオンライン掲載された。
|
|
米Alnylam社、アルツハイマー病のRNAi薬が第1相で持続的な薬力学的効果
from 日経バイオテクONLINE
(2023-7-27 7:00)
|
米Alnylam Pharmaceuticals社は2023年7月17日、アルツハイマー病(AD)または脳アミロイド血管症(CAA)の適応で開発中のRNAi薬(ALN-APP)について、第1相臨床試験の中間解析結果を発表した。単回の髄腔内投与により、バイオマーカーである可溶性アミロイド前駆体蛋白質α(sAPPα)を最大84%、sAPPβを最大90%減少させた。同社は、同年7月16日〜20日にオランダで開催されたアルツハイマー病協会国際会議(2023 AAIC)で詳細なデータを発表した。
|
|
6/25(日)第63回さつき会総会報告
from さつき会〜東大女子ネットワーク・コミュニティ〜
(2023-7-26 12:54)
|
2023年6月25日(日)13時から16時、第63回さつき会総会が開催されました。今年もオンラインで行われ、参加者は講師も含め44名でした。
総会議事では、鵜瀞惠子代表幹事 (1977経)と伊藤紫織会計担当幹事 (1992文)から第 62 期の幹事会・委員会活動報告と決算報告書、監査報告書 、第 63 期の活動計画案 、予算案 ならびに幹事・会計監事の選任案の提示があり、いずれも承認されました。承認は挙手で行われました。
活動報告では、各委員会の活動報告に加えて、2023年5月20日現在の会員数が1144名と増え2019年の数字に戻ったという嬉しい報告もありました。なお、会費滞納による退会判断時期は5年から3年に短縮されました。
活動計画案には、各種イベントの対面・オンライン開催、奨学金制度の広報・運用、1965年卒までの草創期の会員に対するさつきスペシャルインタビューの継続、会員管理の充実などが含まれています。
なお、会計監事は今年度から再任の住田裕子監事(1977法)と新任の野田弘子監事(1984法)の二人体制となります。
ハラスメント防止委員会で検討を重ねてきた、会員の行動規範を会則に盛り込む会 ...
|
|
7/23(日)第14回東大卒業生交流会開催報告
from さつき会〜東大女子ネットワーク・コミュニティ〜
(2023-7-26 11:23)
|
7/23(日)の第14回東大卒業生交流会(婚活支援)は、オンラインにて開催いたしました。
女性11名、男性11名の計22名のご参加でした。
MetaLifeを利用し、自由懇談という形でお話していただきました。
アメリカや関東以外のご参加もありました。
次回は1/14(日)の予定です。
皆様のご参加をお待ちしております。 The post 7/23(日)第14回東大卒業生交流会開催報告 first appeared on さつき会〜東大女子ネットワーク・コミュニティ〜 .
|