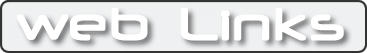リンク
RSS/ATOM 記事 (63409)
ここに表示されている RSS/ATOM 記事を RSS と ATOM で配信しています。


|
JCRファーマ、BBB通過技術を適用したJR-441の第1/2相試験の開始は「目前」
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 7:00)
|
JCRファーマは2023年5月12日に2023年3月期の決算説明会を開催し、開発パイプラインの進捗などを説明した。説明会の冒頭で同社の芦田信代表取締役会長兼社長は、ムコ多糖症IIIA型(サンフィリッポ症候群A型)を対象とした治療薬JR-441について、「臨床入りは目前に控えている」とコメントした。
|
|
日本新薬、2023年度はDMD向け核酸医薬3品目の臨床試験を開始へ
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 7:00)
|
日本新薬は2023年5月11日、2022年度(2023年3月期)の決算を発表した。売上収益は前年同月比4.9%増の1441億円、営業利益は同8.8%減の300億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は同8.7%減の228億円だった。2023年度は売上収益が0.5%増の1450億円、営業利益が6.5%増の320億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は9.6%増の250億円を見込んでいる。
|
|
米UNITY社の老化細胞除去薬、糖尿病黄斑浮腫の第2a相で持続的視力改善
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 7:00)
|
米UNITY Biotechnology社は2023年4月24日、抗アポトーシス蛋白質BCL-xLの低分子阻害薬であるUBX1325が、糖尿病黄斑浮腫(DME)患者を対象とする第2a相臨床試験(BEHOLD試験)において、1回の硝子体内注入で約1年にわたる視力改善効果を示したと発表した。新たな作用機序のDME治療薬として有用性が示唆され、同社は2023年下期に開始する抗VEGF薬対照の第2b相試験を準備している。
|
|
三菱ケミカルG決算、Medicago撤退とMuse開発中止も「ヘルスケアには継続投資」
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 7:00)
|
三菱ケミカルグループは2023年5月12日、2023年3月期(2022年4月〜2023年3月)の決算説明会を開いた。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン開発や、多能性幹細胞「Muse細胞」開発からの撤退が重なった期となったが、今後もバイオ領域に投資を続ける方針を示した。
|
|
武田薬品、AAV遺伝子治療の研究開発プログラムを中止
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 7:00)
|
武田薬品工業は2023年5月11日に2022年度(2023年3月期)の決算発表を行った。売上収益は前年同期比12.8%増の4兆274億円で、営業利益は同6.4%増の4905億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は同37.8%増の3170億円だった。2021年度に日本の糖尿病治療薬ポートフォリオの売却やその他の資産譲渡があったため、その影響を除いたコアベースの売上収益は前年同期よりも17.7%増加した。ただし、為替の影響を除くとコア売上収益は前年同期よりも3.5%の増加だった。
|
|
ベンチャー探訪、エポメッド、EPO受容体を阻害する抗がん薬を開発へ
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 6:58)
|
エポメッド(東京・港)は新規作用機序の抗がん薬の開発を進めている。エポメッドの創設者の1人である安田佳子・近畿大学医学部元教授(現在、ルイ・パストゥール医学研究センターの基礎研究部創薬研究室室長)の研究を基に2018年2月に設立され、現在は高知県を基盤に鉱業、建築土木、アグリビジネス、エネルギー、情報通信(IT)など多角的な事業を手掛ける高知市の入交グループ本社(高知市、入交太郎社長)が50%以上の株式を保有している。
|
|
World Trendアジア、日台企業の連携は、資金力増す台湾企業が主役に
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 6:57)
|
台湾から日本に持ち込まれるのは半導体だけではない。米Biogen社で新薬開発チームを率いていた林國鐘(Ko-Chung Lin)氏が創業した創薬スタートアップの台湾PharmaEssentia社(薬華医薬)は2023年3月、自社開発の真性多血症治療薬「BESREMi」(ロペグインターフェロン アルファ-2b[遺伝子組み換え])について日本での製造販売承認を取得したと発表した。2023年内の販売開始を目指すという。
|
|
パイプライン研究◎多発性骨髄腫治療薬、ここ10年で製品数が急拡大の多発性骨髄腫治療薬、開発パイプライン
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 6:54)
|
多発性骨髄腫(Multiple Myeloma:MM)は、悪性リンパ腫、白血病と並ぶ血液がんの1つで形質細胞のがんである。形質細胞とは、白血球の一種であるB細胞から分化し、抗体の産生を担っているもので、がん化して骨髄腫細胞になると、骨髄の中で増加し、異常免疫グロブリンであるM蛋白質を産生し続ける。
|
|
リポート、台湾、再生医療や遺伝子治療の法整備へ
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 6:53)
|
再生医療や遺伝子治療の研究開発が世界的な盛り上がりを見せている。日本政府が健康・医療戦略推進本部の下に設けた再生・細胞医療・遺伝子治療開発協議会の報告書によると、2020年に6300億円規模だった再生医療や遺伝子治療の市場は、2030年には7.5兆円、2040年には12兆円まで達する見込みだ。そうした市場拡大を見据え、台湾では数年前から、再生医療や遺伝子治療の研究開発を後押しする施策が検討されている。台湾の蔡英文総統は2022年2月、再生医療産業を推進するために、関連する法律を整備すると発表した。そして、厚生労働省に相当する台湾の衛生福利部によって2つの法案が起草され、2023年2月に立法院(国会)へと送られた。現地の報道によると、2023年5月末までの成立に向けて立法院での議論が進んでいるという。
|
|
特集◎ベンチャーキャピタル調査2023(前編)、ベンチャーキャピタル45社の投資方針・実績を大調査、見えて
from 日経バイオテクONLINE
(2023-5-15 6:51)
|
本誌では2018年3~4月に、バイオ・ヘルスケア関連の未上場スタートアップ(以下、バイオスタートアップ)に重点的に投資している国内のベンチャーキャピタル(VC)などを対象にアンケート調査を実施した。それから現在までの5年間、国内外のバイオスタートアップを取り巻く状況は大きく変わった。
|