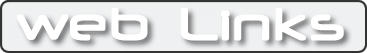リンク
| メイン | 登録する | 人気サイト (top10) | 高評価サイト (top10) | おすすめサイト (8) | 相互リンクサイト (3) |
| カテゴリ一覧 | RSS/ATOM 対応サイト (19) | RSS/ATOM 記事 (63402) | ランダムジャンプ |
RSS/ATOM 記事 (63402)
ここに表示されている RSS/ATOM 記事を RSS と ATOM で配信しています。


| 米3T Biosciences社がシリーズAで58億円調達、TCR関連免疫療法の開発を本格化 from 日経バイオテクONLINE (2022-9-12 7:00) |
|
米3T Biosciences社は2022年8月25日、シリーズAラウンドで4000万ドル(約58億円)を調達したと発表した。T細胞受容体(TCR)をベースとした細胞医薬や抗体医薬などの研究開発を進める。また、ポートフォリオを構築するため、米Stanford Universityからペプチド-白血球抗原(pHLA)標的の抗体ベースの創薬プラットフォーム、および抗MAGE-A3標的TCR発現T細胞(TCR-T)療法の独占的ライセンスを取得したことも明らかにした。
|
| Novo社、ヘモグロビン異常症の疾患修飾薬を開発する米Forma社を1553億円で買収 from 日経バイオテクONLINE (2022-9-12 7:00) |
|
デンマークNovo Nordisk社は2022年9月1日、鎌状赤血球症(SCD)などの希少血液疾患の有力な治療薬候補を有する米Forma Therapeutics社を11億ドル(約1553億円)で買収すると発表した。Novo社は自社が培ってきた希少疾患領域の研究開発において、特にSCDを含むヘモグロビン(Hb)異常症のパイプライン強化を図る。同買収契約に伴う取引は、Forma社の取締役会が全会一致で承認し、2022年第4四半期に終える見通しだ。
|
| 特集◎世界が注目する新規モダリティ、mRNA医薬の可能性、国内の規制におけるmRNA医薬の位置付けは? from 日経バイオテクONLINE (2022-9-12 7:00) |
|
新型コロナを機に、mRNA医薬への関心が高まっている。mRNA医薬の用途は多岐にわたるが、国内の規制で、mRNA医薬はどのような位置付けになるのだろうか──。
|
| ベンチャー探訪、HACARUS、教師データが少なくても高精度解析できる次世代AI技術を医療に応用 from 日経バイオテクONLINE (2022-9-12 7:00) |
|
HACARUS(ハカルス、京都市)は、複数のテクノロジーベンチャーを起業した経歴を持つ藤原健真(けんしん)氏が2014年に創業したスタートアップだ。ビッグデータがなくても人工知能(AI)を使ったデータ解析を可能にする、スパースモデリング技術を医療分野に応用している。既に住友ファーマ系や田辺三菱製薬ともデータ解析で提携しており、国内の複数の国立大学とも共同研究に取り組んでいる。
|
| パイプライン研究、乳がん治療薬、明らかになりつつある第一三共エンハーツの実力 from 日経バイオテクONLINE (2022-9-12 6:59) |
|
世界保健機関(WHO)の研究機関である国際がん研究機関(International Agency for Research on Cancer:IARC)が発表した「The Global Cancer Observatory」によると、2020年の全世界における乳がんの推定死亡者数は68万4996人であった。がんによる死亡者数全体の6.9%を占め、順位は5位となった。2020年には226万1419人が新たに乳がんの患者となり、その割合は全体の11.7%となっている。罹患者数ではトップである。罹患率の国際比較では、東アジアよりも欧米、特に米国白人が高い。米国に移民した日本人の罹患率は、日本国内在住者よりも高い傾向にある。
|
| 特集◎世界が注目する新規モダリティ、mRNA医薬の可能性(後編)、独自調査で分かった国内製薬の動向、複数 from 日経バイオテクONLINE (2022-9-12 6:55) |
|
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するワクチンの開発成功で、国内企業のmRNA医薬への関心が高まっている。現状、mRNA医薬の臨床開発を進めている国内企業(本社が日本にある企業)は、COVID-19にmRNAワクチンを開発している第一三共に限られる。ただ、本誌が国内の製薬企業を対象に実施したアンケート調査では、複数の企業がmRNA医薬の基盤技術の確立やプロジェクトを進めていることが判明した。想定しているmRNA医薬の用途も多岐にわたり、国内の製薬企業が創薬モダリティの1つとして、mRNA医薬を活用しつつある実態が明らかになった(特集前編はこちら、中編はこちら)。
|
| オンライン閲覧TOP15、2022年8月20日から2022年9月2日まで from 日経バイオテクONLINE (2022-9-12 6:53) |
|
2022年8月20日から2022年9月2日までの閲覧数に基づき作成した(本誌に掲載しているオンライン閲覧TOP15を掲載しました)。
|
| バイオベンチャー株価週報、アンジェスがコロナワクチン開発ストップで下落、ステムリムは脳梗塞のアップデ from 日経バイオテクONLINE (2022-9-9 22:00) |
|
日本の株式市場に上場するバイオスタートアップの株価を週ごとにウォッチしていく「バイオベンチャー株価週報」。2022年9月9日金曜日の終値が、前週の週末(9月2日)の終値に比べて上昇したのは35銘柄、不変だったのは3銘柄、下落したのは12銘柄だった。
|
| 理研・ユーグレナなど、ゲノム編集で遊泳しないミドリムシを作出 from 日経バイオテクONLINE (2022-9-9 7:00) |
|
理化学研究所とユーグレナなどからなる研究チームは、ゲノム編集によって、遊泳しないミドリムシを作出したと発表した。培養液中で動き回らないため、液を静置することで沈殿させることができ、回収効率が良いという。論文は2022年9月9日(日本時間)、Plant Biotechnology Journalオンライン版に掲載された。
|
| 慶應大・岡野教授、患者由来iPS細胞でアルツハイマー病モデル脳オルガノイドを作製 from 日経バイオテクONLINE (2022-9-9 7:00) |
|
慶應義塾大学医学部生理学教室の岡野栄之教授、嶋田弘子特任講師らの研究チームが、アルツハイマー病(AD)患者由来のiPS細胞から、アミロイドβとタウの凝集を伴う脳オルガノイドの作製に成功したと発表した。論文は2022年9月8日(米国東部時間EST)、Cell Reports Methods誌オンライン版に掲載された。
|