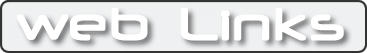|
大阪大学と東京大学による、生命らしさを持つ機械人間「オルタ(Alter)」日本科学未来館で公開
from --ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」 | Online ROBOCON Magazine--
|
大阪大学石黒研究室 と、 東京大学池上研究室 による、生命らしさを持つ機械人間「 オルタ(Alter) 」が 日本科学未来館 で8月6日まで公開されている。「オルタ」は顔から首、手のあたりは皮膚に覆われているが、背中や腕は機械がむき出しだ。何かをしゃべっているように見える。頭部や腕はしきりに動き、背後で流れる音に合っているようにも見える。
日本科学未来館に現在展示中の、生命らしさを持つ機械人間「オルタ」。記者発表の日は、周りを報道陣に囲まれていたので、しきりに動いていたが、周囲の人混みがなくなるとどうなるのだろうか。
大阪大学石黒研究室は、今まで人間そっくりの見た目と動きを持っているアンドロイドを開発しており、日本科学未来館にもオトナロイドとコドモロイドという人間そっくりのアンドロイドを提供している(3階で展示中)。大阪大学大学院 基礎工学研究科の石黒浩教授によると、それらのアンドロイドは、ストレートに人間をまねることで、人の存在感を表現することが目的だったそうだ。しかし、今回は東京大学大学院 総合文化研究科の池上高志教授と共同で、今までのアンドロイドとは異なるアプローチで ...
|
|
8/6-7開催のMaker Faire Tokyo 2016に出展します!
from --ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」 | Online ROBOCON Magazine--
|
8月6日(土)、7日(日)に東京ビッグサイトで開催される「 Maker Faire Tokyo 2016 」に、オーム社も出展いたします!
ブースでは、『ロボコンマガジン』バックナンバーや、モノづくり関連書籍の販売のほかに、イベントも開催します!
現在ロボマガ本誌で連載中の「マイクロマウスではじめよう ロボットプログラミング with ロボット女子会」のイベントでは、連載でも参加していただいているロボット女子会マウス女子部のみなさんが、それぞれご自分のマウスを持って登場、ブースに設置した迷路を走らせます。マウス製作裏話なども伺う予定です。
「アクリルロボット研究所」の三井康亘先生のイベントも開催します。サッカーロボットの体験操縦を行います。三井先生と一緒に遊びませんか?他に、三井先生の作られたアクリルロボットの数々も展示予定。新作のアクリルロボットも見られるかもしれませんよ!?
オーム社ブースの詳細は こちら のページで掲載しています。さらに新しい情報もアップしていきますので、ぜひチェックしてください!
|
|
2016/7/16 北陸支部 夏の研究セミナーのお知らせ
from 生化学若い研究者の会
|
北陸支部主催の夏の研究セミナーを開催することが決定致しましたのでお知らせ致します。 この度、北陸支部単独では初となる講師の先生方をお呼びした、研究セミナーを開催致します。 当セミナーは学部生からポスドクの方までを対象に、様々な研究に触れられる機会を提供するものとなっております。 まず第一部では、それぞれ異なる分野でご活躍されている2名の先生方にお越しいただき、ご自身の研究についてご紹介いただきます。また第二部では、セミナーに参加する学生のうち希望者に研究紹介を行っていただきます。普段の研究生活ではなかなか専門外の研究に触れる機会は少ないかと思います。そこで当セミナーでは、様々な分野の研究に触れる機会を提供し、自身の分野とは異なる考え方を身につけたり、幅広い視野を養う機会になればと考えております。北陸支部以外の方の参加も大歓迎ですので、奮ってご参加ください!! 以下、当セミナーの詳細となります。 生化若手の会 北陸支部・夏の研究セミナー 【主催】生化学若い研究者の会 北陸支部
【日時】2015年7月16日(土) 14時半より(懇親会 18時より)
【会場】新潟大学・五十嵐キャンパス・生命環境棟109 ...
|
|
第4回 日経星新一賞が開催 応募作品募集中!
from --ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」 | Online ROBOCON Magazine--
|
日本経済新聞社主催による文学賞、日経「星新一賞」が今年も開催され、現在作品を募集しています。『ロボコンマガジン』も協力団体として参加しています。
同賞は、「ショートショートの神様」と呼ばれたSF作家・故星新一氏にちなみ、「理系的発想からはじまる文学賞」として2013年に創設され、今回で第四回目を迎えます。
応募規定に
人間以外(人工知能等)の応募作品も受付けます。
とあるように、人工知能(AI)が執筆した作品の応募も受け付けているのが大きな特徴です。実際に2015年に開催された第三回では人工知能が執筆をサポートした作品が一次選考を突破し、大きな話題になりました。今年も再び人工知能により執筆された作品が結果を残せるのか、要注目です。
募集部門
一般部門
■対象
制限なし
■課題
あなたの理系的発想力を存分に発揮して読む人の心を刺激する物語を書いてください。 (規定字数:10,000文字以内)
■応募締切
2016年9月30日(金) 24 : 00
■賞金・賞品
グランプリ( 星新一賞 ) 副賞 100万円
準グランプリ
優秀賞( JBCCホールディングス賞 )
優秀賞( 東京エレクトロン賞 )
優秀賞(アマダホールディング ...
|
|
ビョークの音楽の世界を体感する「Björk Digital-音楽のVR・18日間の実験」、日本科学未来館で開催中
from --ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」 | Online ROBOCON Magazine--
|
日本科学未来館で開催されている「 Björk Digital-音楽のVR・18日間の実験 」は、アイスランド出身のアーティスト・ビョークの音楽と最先端のテクノロジーの融合により、音楽体験を拡張する実験的なVRの展示プロジェクト。メインとなるのは、アルバム「Vulnicula」収録の楽曲をVR作品化したもの。「Stonemilker VR」と「Mouthmantra VR」、「Not Get VR」の3作品で、それぞれの楽曲の世界に引き込まれるような体験ができる。観客はヘッドセットを装着。編集部でも体験をしたが、すぐ隣や目の前でビョークが歌っていたり、楽曲の世界の一部になったように感じられた。
(c)Santiago Felipe
VRコンテンツの体験の様子。
(c)Andrew Thomas Huang
「Stonemilker VR」は、Andrew Thomas Huang監督によりアイスランドで撮影された「VRSE」とうVRアプリの作品。風が吹きさらすなかで、ビョークが「Stonemilker」を歌う。360°の風景のなかかをビョークが移動していくので、見ているこちらは彼女を追いかけて向きを変えていく。
(c)Jesse Kanda
「Mouthmantra VR」はJesse Kanda監督による作品。「Mouth Mantra」を歌うビョークの口の中に ...
|
|
第101回ロボット工学セミナー『やわらかいロボット、やわらかいデバイス - ソフト・ロボティクス入門』 (9/
from --ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」 | Online ROBOCON Magazine--
|
第101回ロボット工学セミナー『やわらかいロボット、やわらかいデバイス - ソフト・ロボティクス入門』 が,2016年9月16日(金)に開催されます.
セミナー口上
本セミナーでは新興分野であるソフトロボティクスに関連する国内研究の最新動向を紹介する.三部構成で,アクチュエータやセンサなどの要素技術から,やわらかさを活かした応用まで,学際的な知識の提供を目指す.関連分野の研究者や,ソフトロボット研究を始めようとする学生,ビジネスの観点からロボット技術の新展開に興味のある企業人を対象とする.
講演内容,タイムスケジュール,申込み方法など,くわしくは以下のWebサイトをご確認ください.
第101回ロボット工学セミナー
やわらかいロボット、やわらかいデバイス - ソフト・ロボティクス入門
■オーガナイザー
新山 龍馬(東京大学)
■日時
2016年9月16日(金)9:30 - 17:30(開場9:00)
■開催地
東京大学 本郷キャンパス 工学部2号館1階213講義室(東京都文京区本郷7-3-1)
会場アクセス
最寄り駅:南北線「東大前」駅または千代田線「根津」駅より徒歩10分、丸ノ内線「本郷3丁目」駅より徒歩15分
■ ...
|
|
『第9回 科学技術におけるロボット教育シンポジウム』が2016年7月23日(土)に開催
from --ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」 | Online ROBOCON Magazine--
|
NPO法人WRO Japan主催による『第9回 科学技術におけるロボット教育シンポジウム』が2016年7月23日(土)に開催されます。それにあわせて、シンポジウムの発表者の募集が行われています。
第9回 科学技術におけるロボット教育シンポジウム
9th Symposium on Robotics in Science and Technology Education
2016年7月23日(土) 科学技術館
◆目的
本シンポジウムは、WRO Japanの目的に沿い、特に小中高校生向けに自律型等ロボットを使った科学技術教育の実践を行っている指導者、支援者のための情報発信、発表および情報交換、交流の場とし、指導者の増加と指導者の実践力のレベルアップを目指します。主に小中高校の教員、指導者を対象とし、さらに小中高校生および教員を支援する高専、専門学校、大学、科学館、企業、NPO等、また社会教育の一環としての実践企業、団体による活発な活動の広がりを目指しています。
◆主催 ・ 共催
・主催 NPO法人WRO Japan
・共催 WRO Japan実行委員会
【WRO Japan】
WRO(ワールド・ロボット・オリンピアード)は、教育的なロボット競技への挑戦を通じて、世界中の若者・子どもたちの参 ...
|
|
2016/07/01北海道支部 蛍光イメージングセミナーのお知らせ
from 生化学若い研究者の会
|
北海道支部では2016年7月1日(金)に北大内の先生をお呼びしてセミナーを開催します。
蛍光イメージングに興味のある方、ぜひご参加ください。もちろん学年や分野は問いません。
お気軽にご参加ください。
|
|
ROBOCON Magazine 2016年7月号
from --ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」 | Online ROBOCON Magazine--
|
Robocon Magazine2016年7月号
■定価:1,080円(本体1,000円+税)
■判型:A4変形判 128頁
■発売日:2016年6月15日
■雑誌:09761
ご購入は、 こちら からどうぞ。
定期購読のお申し込みは、 こちら からお願い致します。
表紙のロボット:ロボティクスファッションクリエイター/メカエンジニアのきゅんくん。手にしているのは今年3月に発表したウェアラブルロボットの「METCALF clione」。本誌では「マイクロマウスではじめよう ロボットプログラミング with ロボット女子会」にロボット女子会の一員として参加していただいています。
写真撮影:其田益成
撮影協力:HAP factory
ヘアメイク:aco(RICCA)
衣装協力:chloma
表紙・目次デザイン:岩郷重力+WONDER WORKZ。
ロボコンマガジン2016年7月号読者プレゼントのお知らせ
お詫びと訂正
■本誌4頁「目次」に記載されている「【Focus】金メダルチームに学ぶ、WROチャレンジのポイント」の著者の所属に誤りがありました。
正しくは、下記のとおりです。
(誤)近藤靖通(愛知県立八幡浜工業高等学校 電気技術科)
(正)近藤靖通(愛媛 ...
|
|
ロボコンマガジン2016年7月号読者プレゼントのお知らせ
from --ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」 | Online ROBOCON Magazine--
|
『ロボコンマガジン』2016年7月号読者プレゼントへのご応募は、2016年8月15日 23:59までです。
アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、下記の賞品を差し上げます。どなた様も奮ってご応募ください。たくさんのご応募、お待ちしております!
応募フォームへ↓↓↓
A賞 『ハウステンボス1Day パスポート』ペアチケット(ご利用期限、2017年3月末まで※9/24、12/31を除く)
1名様 (提供:ハウステンボス株式会社)
B賞 『安川電機「MOTOMAN-SDA10」』
1名様 (提供:安川電機みらい館)
C賞 『Omniホイール 100mm D/ANS』
1名様 (提供:株式会社リバスト)
D賞 『ROBOHON ステッカー』
1名様 (提供:シャープ株式会社)
E賞 『CANDY LINE ステッカー 5枚セット』
4名様 (提供:株式会社 CANDY LINE)
F賞 書籍『柔らかヒューマノイド-ロボットが知能の謎を解き明かす』
書籍『おしゃべりロボット「マグボット」-ラズパイとAr ...
|