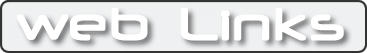リンク
RSS/ATOM 記事 (63398)
ここに表示されている RSS/ATOM 記事を RSS と ATOM で配信しています。


|
英DeepMind社、立体構造予測AIのAlphaFoldデータ件数が2億件に
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-5 7:00)
|
米Google社系列で、蛋白質の立体構造を予測するAIシステム「AlphaFold」を開発、運用している英DeepMind社は2022年7月28日、AlphaFoldのソースコードおよびそれらを用いた蛋白質立体構造のデータベースAlphaFold DBの公開を開始してから1年が経過し、同DBに登録されている蛋白質の構造が、当初の約100万件から2億件超にまで拡大されたことを明らかにした。
|
|
遺伝子治療研究所、米Thermo Fisher社の浮遊系HEK293細胞株を導入
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-5 7:00)
|
米Thermo Fisher Scientific社の日本法人であるサーモフィッシャーサイエンティフィックは、2022年8月4日、同社が保有するアデノ随伴ウイルス(AAV)産生用システムのライセンスを非独占的に許諾する契約を、スタートアップの遺伝子治療研究所(川崎市川崎市、浅井克仁代表取締役)と、2022年3月28日付で締結したと発表した。
|
|
米AlloVir社、株式売却資金で抗多重ウイルス他家T細胞療法の第3相を加速へ
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-5 7:00)
|
他家T細胞免疫療法を開発している米AlloVir社は2022年7月27日、投資家グループと株式売却契約を締結したと発表した。およそ1億2660万ドル(約166億円)分の株式を売却し、得られた資金を第3相臨床試験段階にあるT細胞療法(posoleucel、Viralym-M、ALVR105)の開発加速に向けて活用する。
|
|
World Trendアジア、バイオスタートアップを育む、台湾の未上場株式市場
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-5 7:00)
|
台湾の株式市場で新規公開(IPO)が活況を呈している。2022年前半、各国でIPOが低迷している中、台湾ではIPOの数と資金調達額がどちらも前年同期比で倍増した。上場した27社の調達額は合計で288億台湾ドル(約1325億円、1台湾ドル=4.6円で換算)に上り、1社平均では約50億円となっている。
|
|
株価は語る(5)、時価総額首位の第一三共、HER2低発現乳がんに対するエンハーツ開発で株価が伸長
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-5 7:00)
|
第一三共の時価総額は約6.6兆円に達し(2022年8月4日時点)、長らく首位であった中外製薬を抜いて国内製薬企業の中でトップとなっている。第一三共は抗HER2抗体を用いた抗体薬物複合体(ADC)である「エンハーツ」(トラスツズマブデルクステカン)の開発に力を入れており、HER2陽性乳がんやHER2陽性胃がんなどの疾患で承認を取得している。2022年6月の米臨床腫瘍学会(ASCO)年次総会では、HER2低発現がんを対象とするエンハーツの第3相臨床試験のデータの発表に対して、異例のスタンディングオベーションが沸き起こった。エンハーツの成長とともに同社の株価は好調に推移しており、7月12日には年初来高値の3662円を達成した。
|
|
キーワードを専門誌記者が解説、フリーラジカルとは?
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-5 7:00)
|
不対電子を持つ分子や原子。ミトコンドリアの電子伝達系などで産生される。電子は一般的に対の状態で軌道に収容されているため、フリーラジカルは反応性が高い。脂質、蛋白質、核酸を酸化して、細胞の変性や機能低下を引き起こす。ヒドロキシラジカルやヒドロペルオキシラジカル、スーパーオキシドなどがある。
|
|
クライオ電顕技術のキュライオ、AI創薬のiSiPと業務提携
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-5 7:00)
|
クライオ電子顕微鏡(以下クライオ電顕)を使った創薬研究のキュライオ(東京・新宿、中井基樹代表取締役CEO)は2022年8月5日、AI創薬を手掛けるiSiP(アイシップ、東京・文京、高木悠造代表取締役CEO)と戦略的業務提携契約を結んだと発表した。
|
|
小崎J太郎のカジュアルバイオ、次世代創薬のカギを握る“生体内合成化学治療” 有機合成の場はin vitroから
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-5 7:00)
|
有効性と安全性を確保するために、抗がん薬にはがん細胞に対する高い選択性が要求される。東京工業大学の田中克典主任研究員(理化学研究所主任研究員)は、がん細胞上あるいは内部で薬剤を化学合成することで、その課題の克服を目指している。
|
|
『さつき会ブログ』7月更新のお知らせ
from さつき会〜東京大学女子ネットワーク・コミュニティ〜
(2022-8-4 21:06)
|
猛烈な暑さが続く毎日ですが、お元気でお過ごしでしょうか?
イベント委員会情報発信チームから『さつき会ブログ』7月更新のお知らせです。
7月の更新は次の3件でした。
★ローマンカモミールをお花から楽しむ:ガーデニング
★漱石山房記念館を訪ねて:博物館めぐり
★小石川植物園でのKew garden画家による植物画教室:私の愉しみ
下記URLから是非ご覧ください。
https://satsukikai-joho.fc2.net/
拍手やコメントなど頂けましたら嬉しいです。
※コメントを送付するには、記事のタイトルをクリックして、記事の下に表示されるコメント欄(CM)からお願いします。メール、URL、パスワードなどの記入は必要ありません。
『さつき会ブログ』では会員の皆様からの原稿を募集しています。
原稿は joho-hasshin@satski-kai.net 宛てにメールでお送り頂くか、Googleフォーム( https://forms.gle/Yn8FBiFNcSx3camc9 )を利用してお寄せください。
皆様のとっておきの情報をお待ちしています。
...
|
|
米Versant Ventures社、カナダAbCellera社と抗体探索研究で協力
from 日経バイオテクONLINE
(2022-8-4 7:00)
|
カナダAbCellera社は2022年7月27日、ヘルスケア分野に特化したベンチャーキャピタルである米Versant Ventures社と複数年にわたる協力契約を結んだと発表した。Versant社の投資先であるバイオ企業が選出した、複数の標的に対する治療用抗体の発見に取り組む。
|