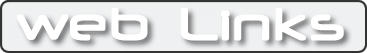|
�������Υꥹ�����������ȸ��椬��ϫ�ʤθ��縦��Ǻ���
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-21 7:00)
|
������ϫƯ�ʳظ���ˡ��������Υꥹ�����������Ȥ�Ԥ�������꤬���줿���Ȥ�ʬ���ä����ꥹ�����������Ȥη�̤Ϻ��塢����������¤��ή�̤˴ؤ���롼����κ����ˤʤ��ǽ�������ꡢ�ȳ��ϵ������ˤι��������ܤ��Ƥ��롣���θ�������ɤ�ª�������ɤ�����2022ǯ6��20��������ϫƯ�ʤ�ô���Ԥ�ʹ������
|
|
�ȳ����ܤ��á�������ǥ����١������3��ζ���Ȥ�
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-21 7:00)
|
����ݳز�ξ�ǰ���Υ�����ǥ����١���������ꡢ����ȤʤäƤ��롣2022ǯ6��˥������dz��Ť��줿�ƹ�������ز��ASCO�ˤ�2022ǯ������Υץ�ʥ���å����ǡ�Memorial Sloan Kettering Cancer Center�˽�°�����դ�Shanu Modi�ȯɽ����ȡ�����ʥۡ�������Ԥ�����İ����¿����Ω���夬�ꡢ��Ӥ����ä���
|
|
�ý������������³�����ܳʻ�����DTx��̤��Ȳ��ꡢ����������Non-SaMD��SaMD��ξ������������ơ��IJ��
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-21 7:00)
|
�����������Ǥ���ƣ�ʲ������ե��������ƥ४�ե�������CECO�ˤ�̳�ᡢIT����������ǥ����륽��塼�����ȯ���Ȥ��ä�DX�ʥǥ�����ȥ�ե���������ˤδ�Ϣ�������ޤȤ�Ƥ��롣�ǥ�����إ륹��ǥ����륻��ԥ塼�ƥ�������DTx�ˤλ��Ȳ��˸���������ȤߤˤĤ��ơ�2022ǯ5��31�����������������������ƣ�ʲ�������ե��������ƥ४�ե�������IT��������Ĺ�ȡ�����������˥С�����ץ�åȥե������������ļ�������Ĺ���ä�ʹ������
|
|
���ӷ뵮�ҤΡ���ϡ���ʪ�����������ʳشط����ȿ������ܲʳؿ��������JAAS�ˡס�����絬�ϥ��٥�Ȥ�
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-20 7:00)
|
������Ԥʤɲʳشط��Ԥǹ��������NPOˡ�ͤΡ����ܲʳؿ��������JAAS�����㡼���ˡפ�2022ǯ6�����礭�ʥ��٥�Ȥ�������1������ȥ��å����եߡ��ƥ����ͤ����ǡ�6��18��19����2���֤����̡�����饤��Υϥ��֥�åɡ�6��20������24���ϥ���饤��Ǽ»ܡ��������ȤϤ����ʤ���ΤΡ���ɴ��ñ�̤Ǥν��Ҥ����������ܻؤ��ֲʳؤκ�ŵ�פȤ��Ƥ�ƻ�����Ƨ�߽Ф�����
|
|
��Alnylam�ҡ�����C5ɸŪRNAi��cemdisiran��IgA�վɸ�����2��ǹ����
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-20 7:00)
|
����Alnylam Pharmaceuticals�Ҥ�2022ǯ6��9������Regeneron Pharmaceuticals�Ҥȶ�Ʊ��ȯ��Ρ�������ʬC5��ɸŪ�Ȥ���RNAi������cemdisiran��ALN-CC5�ˤ�IgA�վɴ��Ԥ���Ϳ������2���ǡ�����̤�����줿��ȯɽ������
|
|
�������������������ʤ�15�ҡ��ȼﲣ��Ū�ʡ�PHR�����ӥ����ȶ���פ���Ω��
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-20 7:00)
|
���������������������ʤ�15�Ҥ�2022ǯ6��16��������ǵ��Բ���PHR�ʥѡ����ʥ�إ륹�쥳���ɡ˥����ӥ����ȼԤˤ�����Τ���Ω�����ȯɽ����������̾�ϡ�PHR�����ӥ����ȶ���ʲ��Ρˡפǡ�2023ǯ���������Ω���ܻؤ���������Ȥ���ŵ����������̿���ҡ��ݸ���Ҥʤɤ����ä��롣PHR�����ӥ����Ȥ�ȯŸ�ȹ�ݶ����Ϥγ�Ω���ܻؤ���3�Ĥ�ʬ�ʲ�ǵ�����ʤ�롣�����Ť����кѻ��Ⱦʤ�ȫ������Ϻ��̳�������ӥ����Ĵ��ϡ��֥ǡ���ɸ�ಽ��롼��������ʤ�뤿�ᡢ�桹�Ȥ��Ƥ����Τ���Ω��ٱ礷�����פȥ����Ȥ�����
|
|
�������������른����ƥå�����ե��֥�¤��Ф��������Ƴ�����Ȼ��ú�˦��Ƴ��
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-20 7:00)
|
�����硼��������ۡ���ǥ����ϡ�2022ǯ6��17�������른����ƥå������ջԡ�����������ɽ�������Ĺ�ˤ��饤���������¤�1�ġ��ե��֥�¤��оݤ˳�ȯ���Ƥ��������Ƴ�����Ȼ��ú�˦��Genetically Modified Adipocyte��GMAC�ˤˤĤ��ơ�Ʊ�һҲ�Ҥΰ��������ȥ��른����ƥå������ܤˤ����붦Ʊ��ȯ����Ӽ»ܸ�������������뤷����ȯɽ���������������Ϸ��������ȼ�����̤μ������оݤȤ���GMAC�γ�ȯ�����丢�˴ؤ��륪�ץ�������������
|
|
��Precision�Ҥ�¾��CAR-T���������Ѽ����1������㤬�ո�
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-20 7:00)
|
����Precision BioSciences�Ҥ�2022ǯ6��8�������Ѽ���Ф���¾�ȥ���鹳��������T��˦��CAR-T����ˡ�Υ�ɳ�ȯ�ʡ�PBCAR0191�ˤˤĤ��ơ���1/2a�������ͭ�ϥǡ�����ȯɽ�������ǿ�����ֲ��Ϥ�11�����Ƥ��ո��������ź����������ꤷ��Ŭ����ǽ�����դ���ǡ���������줿���ޤ����̤�¾��CAR-T��ˡ��PBCAR19B��PBCAR269A�ˤο�Ľ���������餫�ˤ�����
|
|
�ɥ�å��ǥ�����ˤ�����AI���ѡ��������ʤ�SF���ä�
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-20 7:00)
|
������ʻ��֤����Ѥ��פ��뿷���γ�ȯ�����ǽ��AI�ˤDz�®�����뤿��θ��椬�����ȳ��ǿʤ�Ǥ��ޤ���AI��ȯ��ɬ�פȤ����ϡ��ɥ������ȥ��եȥ�������ץ�åȥե�����Ȥ���������NVIDIA�Ҥϸ��ߡ��������������Ȥȶ��Ȥ��Ƥ��ꡢ������ǡ���AstraZeneca��AZ�˼ҤȤ�AI��ǥ�γ�ȯ�ˤ����ƥ���ܥ졼������ʤ�Ƥ��ޤ����ޤ����ѹ����Υ����ѡ�����ԥ塼������https://blogs.nvidia.co.jp/2021/04/15/ai-drug-discovery-astrazeneca-university-florida-health/�ˤȤ���2021ǯ�˱��Ѥ����Ϥ��줿Cambridge-1����Ω�ѡ��ȥʡ��ˤ�ʤäƤ��ޤ���2022ǯ3��˳��Ť��줿NVIDIA�Υ������Х륫��ե����GTC 2022�פǤϡ����������ǥ�ˤ���AZ�ҤΥ衼�ƥܥ긦�������Molecular AI�����Ψ����Ola Engkvist�ʥ��� ���ӥ��ȡ˻���å�����Ԥ��ޤ�������Accelerating Drug Design with AI��AI�ǥɥ�å��ǥ�������®������ˡפ��ꤷ���ܥ��å����Ǥϡ�AZ�Ҥˤ���������ǥ����Ѥ����ǿ��θ������Ƥ䡢�ɥ�å��ǥ������AI����Ѥ����Ǥ������ȤϤɤΤ褦�ʤ��ȤʤΤ����������Ƥ��ꡢ�ܵ����Ǥϡ����Υ��å��������Ƥΰ����� ...
|
|
�Х����٥���㡼�����������Х����ո����ɽ�ǺƤӥ��ȥå⡢�ڥץ��ɥ���1000�߰ռ�������
from ���ХХ����ƥ�ONLINE
(2022-6-17 21:00)
|
�����ܤγ����Ծ�˾�줹��Х����������ȥ��åפγ������Ȥ˥����å����Ƥ����֥Х����٥���㡼��������ס�2022ǯ6��17���������ν��ͤ��������ν�����6��10���ˤν��ͤ���٤ƾ徺�����Τ�4������������Τ�46�������ä���
|